ハナ
「熱っ……!」
途端に顔へ降りかかった紅茶を拭い去る。
その時だった。
頭上から私は怒鳴りつけられたのだ。
紀美子
「何をするの!? 着物が紅茶でよごれてしまったじゃない!」
紀美子
「まったく……トメ! トメはいないの!?」
紀美子様が叫ぶように声を荒げる。
慌ただしくなる食堂内の中、私は浴びた紅茶に驚いたまま身動きが取れなかった。
ハナ
(私……転んだ……?)
そんなはずはない。
私は、紅茶を持って奥様の元へ行こうとしただけで……。
トメ
「いかがなさいました、紀美子様」
紀美子様の金切り声が止んだかと思えばトメさんが静かに食堂へ入ってくる。
紀美子
「この女中が勝手に転んで、あたくしの着物を汚したの」
トメ
「まあ、そんなことが……申し訳ございません。紀美子様」
紀美子
「これだから嫌なのよ、新入りって。トメ、この女中が使い物になるまでは、あたくしの前に出さないようにしてちょうだい」
ハナ
「っ……」
紀美子様の言葉に、紅茶の熱さも忘れ私は息を呑んだ。
紀美子
「よろしくて? あなたがあたくしの前に出ることは金輪際ないことになるかもしれないのよ?」
紀美子
「あたくしの言っている意味、理解出来てるかしら?」
紀美子様はかがんで、未だ立ち上がれない私を見てニヤリとした。
ハナ
「…………」
紀美子
「あらぁ、理解していなさそうね。言葉が通じないのなら話をしても無駄よねぇ」
紀美子
「あなた、女中にむいてないわ。主の着物を汚したのに謝罪の一言もないなんて」
紀美子
「そうよね、所詮は米俵一俵で売られたのと同じような存在だもの。ああ、あなたたち貧乏人にとって米俵一俵なんて大金と同じね。ふふふふ……ああっおっかしい」
紀美子様の言葉が、濁流のごとく頭のなかを流れていく。
わかっている。
何を言われているか、わかっているのに……。
それなのに、反応できない。
体が、動かない……。
紀美子
「よくもまあ、こんな不要な人間を松乃宮の屋敷へ入れたものね。ここまで落ちこぼれの女中が今までいたことがあって?」
トメ
「私の教育不足です。大変申し訳ございません」
違う。
トメさんじゃない。
謝るのは、私……。
それなのに、声が……出ない。
紀美子
「何とか言いなさいよ!」
パシン……乾いた音と共に、頬を引き裂くような痛みを覚えた。
ハナ
(私……今……叩かれた?)
頬がジンジンする。
紀美子
「あなた、叩かれても言葉が出ないの? はぁ、あなたを見ているとイライラして頭がおかしくなりそうだわ」
すっと立ち上がった紀美子様が、頬を押さえたまま呆然とする私に冷酷な視線を落としトメさんを見る。
紀美子
「トメ、早く変えの着物を用意して頂戴。こんな出来損ない見ているのも嫌だわ!」
紀美子
「お母様、あたくし先にお部屋へ戻りますわね」
そう息巻いて紀美子様は足音を立てながら食堂を後にする。
紅茶の熱は、いつの間にか消えていた。
千代
「……静かに食事をしたいものね」
千代
「私も部屋へ戻ります。紅茶は部屋に運びなさい。ただし、この女中以外で」
紀美子様とは違い、静かに席をたった奥様。
けれど、私へ落とした視線は紀美子様と同じだった……。
パタンと扉の閉まる音が聞こえるやいなや、私の肩にそっと誰かの手がかかった。
トメ
「よく、辛抱しました」
ハナ
「トメさん……」
ようやく声が出ると、トメさんは穏やかな目で私を見た。
トメ
「……ハナ、片付けが終わったら離れに来なさい」
ハナ
「え……?」
トメ
「さあさ、皆さん、食事の後片付けを。
若旦那様の分も下げてしまって大丈夫ですよ。
本日はお仕事で遅くなりますから」
トメさんが、動き出す。
それにあわせて、女中も慌ただしく片付けをはじめた。
そんな中、私1人、その場にしゃがみこんでいることしかできなかった。
トメ
「来ましたね」
夜支度を終えた私は、浮かない顔でトメさんの待つ部屋に入った。
トメ
「夕食の時の話を聞かせてちょうだい」
うながされ、対面に座るトメさんに一度だけ目を合わせたのだけれど……私はすぐにうつむいてしまった。
ハナ
(夕食の時の話……)
そう言われても、あの時、何が起きたのかは私自身でもよくわかっていない。
何かに、足をひっかけた感覚は確かにあったのだけれど……食堂に石ころがあるわけでもなく、何につまづいたのかがわからなかった。
トメ
「ハナ」
ハナ
「あ、えっと……夕食の時ですよね……」
ハナ
「……すみません」
トメ
「謝罪を聞いているのではありませんよ。
何があったの?」
ハナ
「つまづいてしまいました」
トメ
「……やはりそうでしたか」
ハナ
「え?」
ため息混じりのトメさんの言葉。
私は思わず顔を上げてトメさんを見た。
ハナ
「やはりって、ど、どういうことですか?」
トメ
「……あなたには、話しておいたほうが良さそうね」
何かを考えるようにトメさんは遠い目を窓ガラスへと向けた。
トメ
「何人かの新米女中があなたのように食堂でつまづき、紀美子様の着物を汚したことがあるの」
トメ
「今までは偶然かと思っていたけれど……紀美子様は女中に対して嫌がらせをわざとしているのでしょうね」
ハナ
「嫌がらせ……?」
トメ
「主である紀美子様に対してこんなことを思ってしまうなんて、あってはならないことですが……」
トメ
「紀美子様は起伏の激しいお方で、時に女中に対し八つ当たりめいたことをするのです」
トメ
「それに耐え切れず、何人もの女中がこのお屋敷を去りました」
ハナ
「あっ……」
脳裏に、トメさんの言葉が過った。
これで、しっくる来る。
あの言葉の本当の意味は、このことだったんだ。
――くれぐれも、自分が女中であることを忘れてはなりませんよ。奥様も紀美子様もハナの主なのですから。
そう。
私は女中。紀美子様は主。
たとえ、私がつまづいたのが紀美子様のしわざだったとしても……逆らうことは許されない。
ハナ
「……どうして紀美子様は私をつまづかせたりなんてしたんでしょう」
トメ
「さあ……虫の居所が悪かったのかしら」
ハナ
「虫の居所が悪いだけで、転ばせられちゃうんですね。女中って」
トメ
「……そうね」
諦めに近い息を漏らしながら、トメさんは小さく呟いた。
トメ
「私たちがお給金をいただけるのは、お屋敷の方々がいてくださるからこそ」
トメ
「あの方たちにとって、私たちは野菜や家畜と同じなのですよ」
ハナ
「野菜と……同じ?」
トメ
「ええ、野菜は水を与えられなければ成長することが出来ない。その水くれをするのは人間でしょう?」
ハナ
「は、はい。そうですね」
トメ
「私たち女中はお給金を与えられなければ生きていけない。そのお給金をくれるのはこのお屋敷の方でしょう?」
ハナ
「…………」
トメさんは私に言い聞かせるように……そうして、自分に言い聞かせるように言葉を続けた。
トメ
「野菜が、主に逆らいますか?そんなこと、しないわよね」
トメ
「野菜に、感情は必要ないのです」
トメ
「野菜となる覚悟が持てなければ、ここでは働けません」
ハナ
「野菜となる覚悟……」
ハナ
「馬鹿らしいです。野菜だなんて……」
トメ
「……そうでしょうね。けれど、その馬鹿らしい覚悟が必要なのですよ。仕事をするということは、そういうことです」
ハナ
「……トメさんも、ううん、ここで働いている人たちは、みんな野菜ですか?」
トメ
「皆、働かねばならぬ人たちですからね。野菜となる覚悟を持たねばならなかったのでしょう」
トメ
「もちろん……私も」
一瞬、トメさんの表情が歪んだ。
トメ
「辛いでしょうが、家族のために辛抱なさい」
家族のために。
その言葉が重く胸にのしかかる。
ハナ
(……そうだ、私は家族のために働かなければいけない)
たとえ、紀美子様に何を言われようとも……我慢しなければいけないのだ。
トメ
「いつか、その辛抱が報われる日が来ますよ」
ハナ
「……トメさんは報われました?」
トメ
「……ええ」
少し考えた後、トメさんはそう答えた。
それから、私の気を紛らわせるためだろうか。
トメさんと他愛のない話をして私は部屋を出た。
ハナ
(そういえば、トメさんていつからこのお屋敷で働いてるんだろう)
部屋を出た瞬間に、そんなことを疑問に思ってしまった。
私のように、年季奉公であればとっくにこのお仕事は辞めてるはずなのに……。
ハナ
(まぁ、考えても仕方ないか。
今日は色々あったし、もう寝よう……)
夜も遅いこの時間。
私は足音を潜めながら大部屋へと向かう。
ここでの生活は、大部屋に数人の女中が寝起きを共にする。
誰もが家族を養うための奉公なせいか、私物もほとんどなく、布団と少しの着替えだけが置かれている部屋だ。
寝る前には特に会話もなく、朝起きても二言、三言交わす程度。
それを淋しいと思う時もあったのだけれど、今日のトメさんの話を聞いて納得した。
感情を無くし、野菜として生活しているからなのだ。
ハナ
(じゃあ……カヨさんはどうしてなんだろう。どうして、あんな笑顔でいられるんだろう)
ハナ
(はあ……考えごとが増えちゃった。ちょっと、夜風にでもあたってこよう)
ハナ
「ふう、いい風……?」
外に出て辺りを見回していると、かすかに足音が聞こえてきた。
女中たちは就寝時間のはずだし、こんな時間に外を歩く人なんて……。
ハナ
(もしかして!)
期待をこめて、足音を探す。
すると、そこには……私が待ちわびていた人物が立っていた。
清人
「ハナさん? どうしたのだ、こんな時間に」
ハナ
「あ、やっぱり若旦那様……」
清人
「やっぱり?」
ハナ
「あ、いえ、なんでもありません。お帰りになってらしたのですね」
清人
「ああ。先程な。食事は済ませてきたから、夜風を浴びながら、これを」
そう言って、若旦那様はお酒をのむ仕草を見せた。
ハナ
「でしたら、何か酒の肴になるようなものをご用意します」
清人
「すっかり女中らしさが身についているじゃないか」
ハナ
「そう……でしょうか?」
若旦那様の言葉に、胸がざわついた。
ハナ
「……私は、女中にむいていないかもしれません」
清人
「ハナさん? 何か、あったのか?」
ハナ
「…………」
何も言わず、うつむいたままの私を覗きこむように、若旦那様がかがんだ。
瞬間、ほのかに懐かしい香りが鼻をくすぐった。
お酒の、香りだ。
酒造が近くにあって、そこから漂う香りとよく似ていた。
ハナ
「もしかして、若旦那様が飲んでいらっしゃるのは「仙元」ですか?」
清人
「ああ、そうだが……ハナさんは酒の銘柄に詳しいのか?」
ハナ
「詳しいわけじゃなくて、実家のすぐ近くの酒造と、若旦那様が同じ香りしたので。もしかして、と」
清人
「実家の近く? そうか、この酒はハナさんの故郷の味なのか」
ハナ
「故郷の味……そう言われればそうかもしれません」
清人
「そうか、なら、どうだ?」
そう言った若旦那様が私の前に杯を出した。
ハナ
「飲めないんです」
清人
「なんだ、下戸なのか。ならば仕方がないな。無理強いするものでもないし」
若旦那様は、私へ向けていた盃から、ぐいっと飲み干した。
そうして夜風に乗って香る日本酒に、泣きそうになってしまう。
感情を殺す。
野菜になる。
……私は、本当にそんなことが出来るの?
本当に……勤めあげることが出来るの?
清人
「……ハナさん、どうした」
ハナ
「え?」
清人
「泣いているぞ」
ハナ
「あっ」
気がつけば、香りに故郷を感じ、懐かしさと苦しさで私は涙を流していたのだった。
清人
「勤めは、辛いか?」
ハナ
「……私、むいてないかもしれませんね、女中の仕事に」
ハナ
「かと言って、他に仕事なんて畑仕事ぐらいしか出来ないし……辛くたって、我慢しなきゃいけないのに……」
話をしているうちに、涙がとめどなく溢れてきてしまう。
紀美子様にされたこと。
奥様の視線。
私は、本当に……辛抱できるのだろうか。
ハナ
「申し訳ございません。若旦那様を前に……弱音など」
清人
「別に構わない。私の前だ、気楽に話をしたまえ」
ハナ
「若旦那様……」
漆黒の闇と煌々と輝く月。
そんな夜が、とても似合う旦那様にじっと見つめられ……少しだけ、私の心は軽くなった。
清人
「さ、話そう」
ハナ
「はい」
若旦那様に手招かれ、私はその隣に座った。

↑こちらのタイトルの目次は此方へ

↑その他のタイトルは此方へ












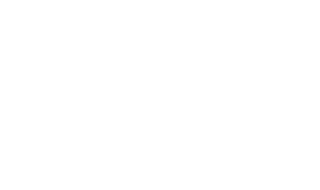
 close
close