ハナ
「いつの間にか……外の景色が一変してる」
2階の廊下を掃除している時だった。
ふと、外を見るとそこから見える
庭の草花は姿を変えていた。
それは、季節が変わったことを
表していて……。
ハナ
(なんだかんだで、このお屋敷に勤め始めて一ヶ月以上ね)
若旦那様に良くしてもらったり、
紀美子様に辛く当たられたり、
カヨさんに仲良くしてもらったり。
それから、直哉さんと街でばったり会ったり。
村を出てから、たくさんのことが起きている。
カヨ
「ハナ、今日は食堂を頼んだよ」
ハナ
「え?」
掃除をしている私に声をかけてきたのはカヨさんだった。
ハナ
「あの、でも私……まだ、食堂のお世話をしていいと言われて無くて……」
カヨ
「紀美子様が直々に、ハナを食事係にしろって」
ハナ
「え?」
カヨ
「……嫌な予感がするんだ。かと言って、紀美子様直々の命令を無下にすることなんてできないでしょ?」
カヨ
「用心するんだよ、ハナ」
ハナ
「嫌だなぁ」
思わず、私が口にするとカヨさんはきょとんとした後、お腹を抱えて笑い出した。
カヨ
「あんた意外と言うねぇ。あっはは、おっかしい」
ハナ
「あ、やだ……私ってば……」
カヨ
「あぁ、気にしなくていいよ。みーんな思ってるって」
カヨ
「じゃ、また食堂でね」
私を気にかけてくれるのかカヨさんは階段のところで1度、手を振ってくれた。
ハナ
(頑張ろう……)
紀美子様はきっと私に何かをしてくるつもり。
けれど、私は1人じゃない。
カヨさんがいる。
女中仲間がいる。
それに、いつだって……直哉さんがいてくれる。
カヨ
「それじゃあ、紀美子様が来たらスープをお願いね」
ハナ
「はい」
気が重いままに、夕食の支度が始まる。
トメさんが奥様たちを呼んでくれば……きっと、紀美子様はすぐに何かをしてくるだろう。
紀美子様とは、あの日、直哉さんと一緒に会った日以来、顔を合わせていない。
きっと、あの日のことも言われるのだろう。
そう思うと、溜息をつかずにはいられなかった。
と、私の息が落ちると同時に扉がゆっくり開く。
私たちは、無表情のままに姿勢を正した。
ハナ
「あ……」
だけど、扉を開けたのはトメさんでも、奥様でも、もちろん紀美子様でもなくて……。
カヨ
「珍しいわね、若旦那様がこの時間に食堂へ来るなんて」
隣でカヨさんが小さく言う。
清人
「ああ、ハナさん。すまないが水をくれないか?」
ハナ
「へ? あ、はい! ただいま」
席につくなり、若旦那様は私の名前を口にした。
まさか呼ばれるなどと思わなかった私は、声を裏返したまま返事をしてしまう。
清人
「何もそう緊張するな」
ハナ
「え?」
清人
「水を差す手が震えている」
ハナ
「あ……」
清人
「……今日はこの時間に食堂へ来て正解だったな」
水を注ぎ終えると、若旦那様は小声でそう言い、グラスを手にした。
ハナ
「あの……どういう意味ですか?」
清人
「紀美子が、君を食事係に指名したと聞いたからな。何かあると思って食堂へ来てみたんだ」
清人
「……そのせいで、緊張しているんだろう?」
ハナ
「…………」
若旦那様の問いに、押し黙ってしまう。
この人は、この家の良心とまで言われる存在。
私の緊張している理由だって口にしなくたってわかってくれる。
だけど、それに甘えてしまっていいのだろうか。
若旦那様も、私の主なのは変わりがないのだから。
清人
「ハナさん、今日は安心していい。私がいる。紀美子には好き勝手させない」
ハナ
「若旦那様……」
清人
「この前は、守れなかったからな」
若旦那様の言葉に心が落ち着く。
手の震えも、いつの間にかおさまっていた。
そうして、元の場所まで戻ると再び扉が開く。
千代
「あら、清人さん」
紀美子
「珍しいわね、お兄様がこの時間に食堂にいるなんて」
清人
「たまには、家族と食事をしたいと思うのは当然だろう?」
紀美子
「あら、あたくしたちのことを家族だと思っていらしたの?
いつも仕事仕事で、まともに顔をあわせないくせに」
ハナ
(え……?
紀美子様と若旦那様って……仲悪いの?)
紀美子
「ああ、それともハナがいるからかしら?」
清人
「なんの話だ?」
紀美子
「お兄様、ハナのことをずいぶんと気にかけているらしいじゃない。なんでも、駅まで迎えに行ったんでしょう?」
清人
「たまたま、あの日は駅の方で用事があったからな。ついでだ」
千代
「ついでだとしても、軽率な行動は謹んでくださいな。あなたは、松乃宮家の次期当主なのですから」
紀美子
「そうですわ。松乃宮の長男なんですから。ねぇ? お母様」
意地の悪い視線を私、そうして若旦那様に向けた紀美子様。
私のせいで、若旦那様が悪く言われている現実に耳を塞ぎたくなる。
紀美子
「まあ、いいわ。それより、早く食事の準備をしてちょうだい。ハナ、スープを」
ハナ
「はい。ただいま」
少しでも、働きを認めてもらわなければ。
そうしなければ……紀美子様は若旦那様にだってもっと辛く当たる。
ハナ
「本日は、野菜のブイヨンスープでございます」
紀美子
「ふぅん。そう」
興味なさそうにつぶやいた紀美子様はスプーンに一口よそり、少しだけすすった。
紀美子
「何!? このスープは!冷めているわ!!」
口に入れたのとほぼ同時だった。
紀美子様はわめくように言ったかと思えば、力いっぱいスープの器を腕でなぎ倒した。
ハナ
「きゃっ」
器からこぼれたスープは、その勢いを衰えることもなく私の手に思い切りかかった。
清人
「紀美子!!」
その様を見ていた若旦那様が、憤慨したままに席を立ち上がったのだが、悪びれる様子もなく紀美子様は前菜に手を付ける。
紀美子
「あらぁ、お兄様どうなさったの?
そんな目くじらたてることないじゃない。冷めたスープだしたハナが悪いのよ?」
ハナ
(冷めてなんか……)
清人
「冷めたスープだったら、何故ハナさんの手が赤くなっている!?」
紀美子
「知らないわよ」
清人
「紀美子!!」
千代
「はぁ、清人さん……いちいち女中の手が赤くなったくらいで騒ぎ過ぎですよ。悪いのはその女中でしょう、温度も確かめもせずに主にスープを出したのですから」
清人
「紀美子は、熱いスープを冷めていると払ったんですよ?」
千代
「なら、紀美子には冷めてると感じたのでしょう」
紀美子
「そうよ! 私には冷めていたの!」
清人
「なら、今度からお前にはもっと熱いスープを用意しないとだな」
紀美子
「なっ……。な、何よ!
だ、だいたいこれぐらいでどうしてお兄様が騒ぎ立てるの!?」
清人
「私でなくとも騒ぎ立てるだろう。少なくとも、人間の感情を持ち合わせていれば」
紀美子
「……気に入らないわ。どうしてお兄様はハナの肩ばかり持つの!?
どうして、こんな田舎の使えない女を守ろうとするの!?
まさか……この女に肩入れするような気持ちでもあって?」
清人
「くだらない戯言には付き合っていられない。私がハナさんをどう思おうが私の自由だ」
清人
「ただ、少なくとも今回のことに関してはハナさんに非などどこにもないだろう?」
紀美子
「あ、あるわよ! そもそもハナなんてその存在自体が、あたくしにとっては失礼なの!!」
千代
「まったく、その女中が食堂にいる日はうるさくてかないわね」
ハナ
「も、申し訳ございません……」
清人
「ハナさん、謝る必要はない。それよりも、手当をしないと。トメ、私の分の食事を一旦下げておいてくれ」
トメ
「ま、若旦那様……なりません。ハナの手当は私がしますのでお食事を」
清人
「悪いが、非情な妹と顔を突き合わせての食事は食欲がうせてしまうからな」
見たこともない、冷酷な視線を紀美子様に落とした若旦那様が、そのまま立ち上がり私の赤くなった手をとった。
清人
「ハナさん、手当を」
ハナ
「あ、あの、でも……」
清人
「いいから」
少し強引気味に私の腕を引っ張る若旦那様の気迫におされ、私はそのまま食堂を後にした。
清人
「痛みはひいたか?」
ハナ
「は、はい」
食堂を出るなり、厨房からありったけの氷を持ち、若旦那様の部屋まで通された。
清人
「……すまなかったな」
ハナ
「若旦那様……」
清人
「何かしでかすとは思っていたが、まさか危害まで加えるとは……我が妹ながら情けない」
ハナ
「いえ、あの……私が至らなかったからですし……」
清人
「そう卑屈になるのはやめたまえ。ハナさんはよくやっている」
ハナ
「……若旦那様は、お優しいですね」
清人
「どうだか。今の今まで私は紀美子にいびられる女中に手を差し伸べることが出来なかったからな」
悲しそうな表情で、若旦那様がポツリとこぼした。
清人
「知っていたんだ。紀美子や母様の仕打ちが原因でこの屋敷を去っていく女中がいたことを」
清人
「けれど、私はそれを見て見ぬふりをしていた……」
清人
「そんな時だった。仕事で付き合いのある人から、とあることを聞かされたんだ」
ハナ
「とあること……?」
静かに頷いた若旦那様は、そっとまぶたを閉じた。
まるで、記憶を手繰るように。
そうして私の手を優しく包み込む。
清人
「この屋敷で女中をしていた若い娘は、実家に帰ったものの吉原に売られたそうだ」
ハナ
「っ!」
清人
「結果、彼女は自らの命を断った。家族に対する恨み言、そうして松乃宮に対する恨み言を残して」
ハナ
「え……?」
清人
「憎悪に満ちた死に顔だったそうだ」
清人
「恥ずかしい話だが、それまで女中に対しては特に思い入れなどなかった」
清人
「しかし……その話を聞いてからは、女中に対しての考え方が変わったんだ」
ハナ
「そのようなことがあったのですね……」
若旦那様の話は、作り話ではないだろう。
直哉さんも、似たようなことを言っていたから。
清人
「だから、ハナさん……君を守らせてほしいんだ。君に、その死んでいった女中のような苦しい思いをさせたくないんだ」
清人
「……これからは、何かあったらすぐ私に言ってほしい」
ハナ
「毎日報告しちゃうかもしれませんね」
清人
「それでもいい。必要以上に耐えることはなにもないのだから」
ハナ
「ですが……若旦那様もお仕事がお忙しいではありませんか」
ハナ
「若旦那様は主なのですから、女中のことなど気にかけていては……」
清人
「主だ女中だと、たとえ身分が違えども私たちは同じ人間だ」
ハナ
「若旦那様……」
清人
「どうした? 何を驚いている?」
ハナ
「い、いえ……紀美子様とは大違いだな、と。その、すみません」
清人
「いや、その通りだからな」
若旦那様が小さく笑う。
それにつられて、私も笑い声を漏らしてしまった。
清人
「あれでも、昔は可愛い妹だったんだ」
ハナ
「そ、そうなんですか!?」
清人
「はは、見事なくらいの驚き様だな」
ハナ
「あ……失礼しました」
清人
「いい。いちいち謝るな」
ハナ
「は、はあ……」
清人
「ハナさん、この部屋にいる間は立場の違いは忘れてくれ」
ハナ
「え、ですが」
清人
「いいから。今は女中という立場を忘れて私の話を聞いてくれ」
私の言葉を遮った若旦那様の真剣な眼差しに、自然と首が縦に動く。
清人
「とりあえず、紀美子の昔話でもするか。あいつがああなってしまった原因は私にもあるからな」

↑こちらのタイトルの目次は此方へ

↑その他のタイトルは此方へ












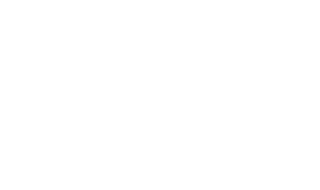
 close
close