【天使の三部作】
ほんとうは出版時期に合わせてリアルタイムで読むべき小説であるのかもしれない。村山由佳のいわゆる「天使三部作」のことである。
デビュー作『天使の卵』に始まり、『天使の梯子』、『天使の棺』と続いたこのシリーズは、村山由佳的なるもののすべてが込められてた名作だ。
初めの『天使の卵』がミリオンセラーを達成してから、完結編『天使の棺』が刊行されるまで、実に20年弱。それだけ、時間と手間をかけて描かれるべきシリーズだった、ということができるに違いない。
思えば、村山はデビュー時、「格調高い文学でなくていい。全ての人を感動させられなくてもいい。ただ、読んでくれた人のうち、ほんの何人かでいいから心から感動してくれるような、無茶苦茶せつない小説が書きたい」と語ったものだった。
その意志は、約20年後の『天使の棺』においても、何も変わってはいない。そこにあるものは、恋の切なさだけを切り取って言葉にしたような、センチメンタルな物語だ。
しかし、村山が20年間にわたって作家として生きのこってきた事実は、彼女の作品がただ「泣ける」だけの甘ったるい代物ではありえないことを示している。
【激情の作家】
村山由佳は、激情を描く作家である。恋とか愛とかいう以前にあって、ひとを果てしなく遠いところまで連れて行ってしまう激しい想いを、彼女は好んで描く。
いま、村山にとって最大のベストセラーでありつづけている『天使の卵』は、あえていうなら若書きの小説であった。そこにあるものは、あまりにもピュアで壊れやすいひとつの想いだ。
恋というなら恋なのだろうし、愛というなら愛でもあるのだろうが、そういったわかりやすい言葉には収まり切らない切ない想い。「無茶苦茶せつない」感情。
だが、この時点では、村山の筆力はその想いを十全に伝え切るには、まだ未熟だったといわざるをえない。物語の構成もシンプルで、あまり脇に外れない。
文章も、流麗ではあるが、さほど面白みがあるものではない。それから十年後の『天使の梯子』は、そこからじつに長足の進歩を遂げている。
『天使の梯子』の主人公は、『天使の卵』のヒロインのひとり、夏姫の教え子だった青年だ。
かれと夏姫の恋を通じて、姉春妃の死後、この世界に残されてしまった夏姫と、十年前、夏姫をあざむいて春妃との恋に溺れていた歩太の十年間が綴られていく。
そこでは十年もの時がなお癒やし切れない哀しみがひたすらに語られる。
【ひとの心の溶鉱炉】
村山は恋愛小説の名手として知られているが、僕は、彼女が書いているものがそんなフレームで括りきれるものだと思ったことはない。
村山が描くものは、けっして洒落た都会的な恋の一幕などではないのだ。
彼女が言葉を尽くして綴ろうとするのは、いつも、人の心のなかに燃える灼熱の溶鉱炉である。ある人は、それを「恋」と呼び、べつの人は「愛」と名づけるかもしれない。
しかしそれは同時に欲望であり、快楽であり、嫉妬であり、憎悪であり、嘆きであり、怒りであり、後ろめたさであり、そして哀しみでもあるのだ。
それらすべてを抱えて、物語は続いていく。『天使の梯子』はその灼熱を描き切っている。
そして、そのさらに後に続く『天使の棺』は、歩太や夏姫とはまったく世代が違うひとりの少女が主人公となっている。
彼女は、歩太と夏姫、それに春妃の物語を知らない。知らないままに、歩太の心を癒やしていく。十年もの歳月を経て、ついに癒やされることはありえないとだけ描かれたあの傷が、彼女の登場によって、ようやく癒やされることになるのだ。
それでは、永遠にじくじくと痛みつづけるものと思われたあの傷ですら、時は回復させてしまうのだろうか。そう思ったとき、ぼくは泣けて来て仕方なかった。
【時の慰撫】
この作品は、ある意味では、いつのまにか遥かに流れ去ってしまった「時」そのものを主人公にしているということもできるだろう。
永遠に変わらないように思えるものも、いつしか必ず変化してゆく――それは、ある種の「喪失」でもあるが、一方で「獲得」であることもある。
ひとはみなかぎりなく長い時の大河の岸を歩みつづける旅人。どんなに辛い出来事も、やがては過去になっていくのだ。
それを、哀しいと嘆く人もいるだろう。ひとつの想いが、永遠に変わらず続いていくことを望む人もいるには違いない。けれど、村山はそういう「純愛」を描写しない。
彼女が描くものは、時を経てより深く、よりあざやかになりながら、それでも治ってゆくひとつの喪失感だ。
繰り返すなら、その喪失感と回復をより切実に体験するためには、出版時期と合わせて読むことがベストではあったに違いない。
けれど、いまからでもまだ十分に間に合う。世にも美しい「天使三部作」の純白の表紙を手に取ってみよう。そこには「無茶苦茶せつない」ひとつながりの物語がある。
もはやただ「面白い」とか「泣ける」といって済ませるにはあまりにリアルになってしまった、「もうひとつの時の流れ」がそこには確実に存在しているのだ。
どうか読んでほしい。おそらくひとの人生をも変える力を秘めた、「無茶苦茶せつない」小説たちである。









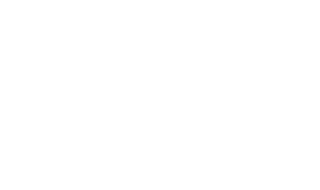
 close
close