プロローグ

まだ春浅い雪の残る会津の涙橋の袂で冨貴子は川下に流れていく簪をただじっと見つめていた。
昭夫と過ごした日々の思い出が走馬灯のように次から次へと冨貴子の頭の中を駆け巡る。
「昭夫さん なしてオラ達幸せになれなかったんだべかなぁ…」とふと呟くと、足元に残る雪の結晶がキラリと輝いた。
まるでそれは亡き昭夫からの伝言のように冨貴子には思えた…

第一章

昭夫は大正十五年九月二日 福島県会津若松市七日町の漆塗り職人夫妻の四人兄弟の末っ子として産まれた。一方、冨貴子は昭和五年一年月十八日に七日町から程近い朝日町にある呉服問屋の一人娘として産まれた。
二人が出会ったのは冨貴子がまだよちよち歩きをしていた頃で、妹のいない昭夫は、笠間稲荷神社まで母に手を引かれて遊びに来る冨貴子をとても可愛いがり、会う度に「あんつぁ めげぇなぁ〜」と頭を撫でて抱き上げた。
そんな兄のように優しい昭夫に冨貴子はすぐに懐き、昭夫に会いたくて、さっさと草履を履いて一人で外へ出てしまうことも度々あった。
冨貴子が五歳になる頃には二人で鶴ヶ城の八重桜を観に出掛けることもあった。冨貴子が七歳になると白虎隊の聖地である飯盛山まで歩いたりもした。昭夫は一生懸命に白虎隊の話を身振り手振りをつけて話すのだが、冨貴子はその姿がおかしくて、ケラケラと笑うだけでちっとも話の内容など聞いていなかった。それでも、昭夫にとっては冨貴子が笑ってくれるだけで満足だった。
そんな平和な日々は数年続いた。幼かった二人は成長して異性であることを意識するようになり、互いに淡い恋心を抱くようになった。恥ずかしがり屋な冨貴子は頬を赤らめて離れて歩こうとするので、昭夫に「こっちさ こ〜!」と手を引っ張られてようやく昭夫の傍にぴったりとくっつくのだった。
昭夫の体温が直に伝わってくるだけで冨貴子は幸せだった。昭夫もまた同じだった。そんな二人は、時には互いに手を重ねあって笠間稲荷神社の広い空き地に寝転んでは 「大人になったら一緒になろうね」などと話したりもした。
この時の二人はまだ日本に暗黒の時代が訪れることも、冨貴子の身の上に一大事が起きることも知らずに平和な日々と幸せはずっとずっと続くと信じていたのだった。

第二章

それから数カ月後のこと、冨貴子の家が飢饉によって着物を買い付ける客が激減したことから倒産に追い込まれた。あちこちから借金を重ねて何とか繋いで来たものの既に限界が来ていたのだった。
それからというもの、父親は毎日金策に夜中まで出歩き、母は箪笥を開けては着物一枚一枚を手に取り質屋に持って行く日々が続いた。
しかし、役人がやって来て着物から箪笥から家財道具一式全て差し押さえられてしまい.立ち退きまで命じられ冨貴子達親子は父の実家でもある叔父夫婦の農家のある門田に引っ越すことになった。
叔父夫婦は冨貴子達親子を快く迎えてくれ、数日間は穏やかな日が続いた。しかし、冨貴子達の居場所はすぐに突き止められ、取り立て人が毎日やって来るようになった。
冨貴子の両親の襟首をつかんで怒鳴り散らしたり、そこいら中蹴飛ばして両親を脅した。冨貴子はその度に怖くて大人達の隙間からそっと外へ抜け出しかわらに隠れるのだった。
それからしばらくして冨貴子が朝目を覚ますと、叔父と父がちゃぶ台を囲んでヒソヒソ話をしていた。柱の影に隠れて聞いていた冨貴子だが、すぐに見つかってしまい、父に「こっちゃ こ!」と手招きされ仕方なく父の隣に座った。
ただ為らぬ空気に冨貴子は嫌な予感がした。そして、それは的中していたのだった。
父は冨貴子に「冨貴子〜磐見町さいぐんだ。」と一言だけ言うと後は黙りこくって下を向いてしまった。すると、すかさず叔父が「まんま 食べなんしょ。したっけが連れてぐから…」と言って茶箪笥にしまってあったおむすびとお芋のふかしたのを持ってきて冨貴子の前に置いた。
米はこの時は高級品で普段はあわやひえを食べるのが通常だったが、叔母が最後だからと冨貴子のために真っ白な米を炊いて握ってくれたのだった。
冨貴子はお腹は減ってはいなかったが、夢中でおむすびと芋を食べた。食べながら涙がポロポロと流れ落ちた。それでも口の中いっぱいに何か入れずにはいられない程 胸が張り裂けそうな想いだった。
冨貴子が食べ終える頃、叔母が畑仕事から戻ってきて急いで部屋に上がり仏壇から何かを取ると、冨貴子に「ちょっとこっちさこ。」と手招きした。
冨貴子が傍まで行くと、叔母は冨貴子に小さな半紙の包みを渡した。なんだろうと開いてみると御守りが入っていた。畑仕事の帰りにお寺に寄って御守りを買って来ていてくれたのだった。
叔母は冨貴子の両手を握りしめて 「うちさも 飢饉からやっと立ち直ったとこだで、じぇにっこね〜がら 堪忍な...」と深々と頭を下げた。叔母の眼からも涙が溢れ落ちていた。
母は冨貴子に会わせる顔がないと「寺にお経さきぎにいぐ」と朝から出掛けていて、冨貴子が家を出る時にも戻ることはなかった。
冨貴子は叔父に連れられ花街である磐見町へと向かった。雲一つない蒼い空がどこまでも拡がり、磐梯山には緑が鮮やかに茂る 初夏の訪れを感じる日のことだった。
冨貴子は叔父と共にただ黙って木々の生い茂る山道を淡々と歩いた。途中、草履の鼻緒で足の指が擦りむけて血が滲んでいたが冨貴子の心は痛みさえ感じない程、緊張と落胆と不安と絶望感でいっぱいだった。
そして、何も考えるまいと思っていた冨貴子だったが、ようやく磐見町近くの七日町に着き、昭夫とよく遊んだ笠間稲荷神社の傍を通ると涙が溢れてきて止まらなくなった。冨貴子は叔父に気付かれまいと袂で涙を擦り顔を隠した。

第三章

冨貴子が連れて行かれた店は会津で有名な花魅である紫紺太夫のいた松風楼の跡地に建てられた朱雀楼だった。叔父は女将に挨拶し、冨貴子を手渡しお金を受け取ると何も言わずにすぐさま帰って行った。
その日から冨貴子は一人前の芸妓になるために、芸事を習いながら掃除から飯炊きまで手伝い、夜は疲れて床に入らず畳の上でそのまま寝てしまうことも度々あった。「遊女とはいえ芸事が立派に出来なければ客はとれない」と女将に厳しく言われ.毎日何とか指導についていくだけで冨貴子には精一杯だった。そして、夜中にふと目を覚ますといつも昭夫を思い出しては唇を噛み締めて静かに泣くのだった。
一方 昭夫は会津中学校を首席で卒業し実家の漆塗仕事を手伝っていた。植物の研究に残らないかと声をかけられたが、家の仕事が手が足りないと断わったのだった。冨貴子の家の事情は噂で聞いてはいたものの、その後の消息については誰に聞いても教えては貰えず、毎日を悶々と過ごしていた。元気でいてくれたらいいと祈りながら。
其の二に続く。。。



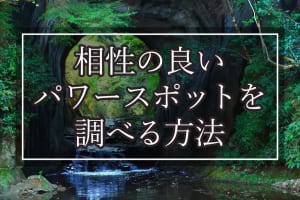





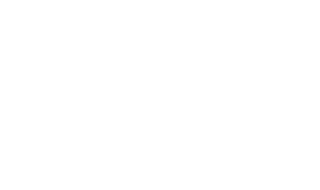
 close
close